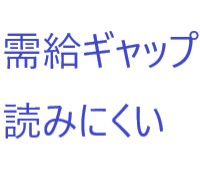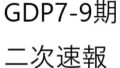以前「内閣府のGDPギャップがプラスに転じたそうです」という記事で、需給ギャップがプラスに転じた事をお伝えしました。
「GDPギャップ」と「需給ギャップ」の違い
この記事を書いたとき、私は「GDPギャップ」と「需給ギャップ」は同じ物だと思っていましたが、よく調べて見ると、両者は異なる指標だそうです。
ChatGPTに質問してみると、以下のような回答を得られました。
GDPギャップと需給ギャップは、似ているようで異なる概念です。これらは経済学で使われる用語であり、異なる側面を指しています。
1. GDPギャップ
GDPギャップは、実際の国内総生産(GDP)が潜在的な国内総生産に比べてどれだけ離れているかを示す指標です。潜在的な国内総生産は、経済が完全雇用状態にあると仮定したときに達成できる最大の生産レベルです。したがって、GDPギャップは、経済が完全雇用状態からどれだけ離れているかを示し、それが景気の拡大または縮小を示す一つの指標です。
2. 需給ギャップ
需給ギャップは、経済の総需要と供給のバランスに焦点を当てています。経済が完全雇用にある場合、需要と供給は一致しますが、現実の経済ではこれが必ずしも実現されません。需給ギャップは、需要と供給のバランスがどれだけずれているかを示すもので、これがインフレーション(需要が供給を上回る場合)またはデフレーション(供給が需要を上回る場合)の兆候となります。
要するに、GDPギャップは主に生産と雇用に焦点を当て、完全雇用状態からの経済のずれを測定します。一方で、需給ギャップは需要と供給の不均衡に焦点を当て、これが価格水準やインフレーションの動きにどのように影響するかを示します。
GDPギャップの潜在供給能力は通常、「潜在的な国内総生産」とも呼ばれ、経済が完全雇用状態にあると仮定したときに達成できる最大の生産レベルを指します。これは通常、経済が全ての生産要素(資本、労働、技術)を最大限に利用し、失業が最小限に抑えられている状態です。
一方で、需給ギャップの供給能力は通常、通常の生産能力または短期的な生産能力と解釈されます。これは、経済が完全雇用にあるとは仮定されていないため、失業が存在する可能性があります。また、需給ギャップは需要と供給の不均衡を指すため、長期的な供給能力のずれとは異なることに留意する必要があります。
簡潔に言えば、GDPギャップの潜在供給能力は通常、長期的な最大生産能力を示しますが、需給ギャップの供給能力は通常、より短期的で一般的な生産能力を指します。
内閣府の発表している「需給ギャップ」は後者の需給ギャップです。
これは、潜在供給能力がGDPギャップのように最大値を示すものではなく、工場や労働者などが、通常運転している状態の供給能力を基準に、ギャップを計算します。
戦闘機の速度の仕様に「最高速度」と「巡航速度」という説明がありますが、最高速度はアフターバーナーを使用して得られる速度を意味し、通常飛行で得られる速度は巡航速度になります。
GDPギャップが想定する潜在供給能力は「最高速度」みたいなもので、需給ギャップの想定する潜在供給能力は「巡航速度」のようなもの、と説明すると分かりやすいと思います。
つまり、今の日本経済は需給ギャップがプラスに転じたものの、想定する潜在供給能力は「巡航速度」の生産能力で、「最高速度」の生産能力ではない為、生産能力にはまだまだ余裕があると言えます。
生産能力に余裕があるという事は、人手不足の逼迫から来る労働者の賃金上昇圧力がまだまだ弱い事を意味します。
需給ギャップは確実に上昇しており、良い方向へ向かっているのですが、まだまだ長期的安定的インフレ目標達成には遠いようです。
「需給ギャップ」と「GDPギャップ」は、経済学者やエコノミストの方々でも、あまり厳密に使い分けているようには見えません。
それほど、両者の違いに拘る必要は無いのかもしれませんが、一応は両者の違いは頭の片隅に入れておいた方が良さそうです。
永濱 利廣さんの需給ギャップ評価
需給ギャップは、エコノミストの永濱 利廣さんが以下の(無料)記事で解説しています。
日本のGDPギャップは過小推計の可能性~2%インフレ目標達成に必要なGDPギャップは+4%程度か~
関連部分を以下に引用します。
<前略>
潜在GDPの試算において、供給力の天井ではなく実績値に基づく過去のトレンドが用いられている。このため、推計期間の直近に近い時期に需要の大きな落ち込みが起こると、潜在GDPの試算値には下方バイアスがかかりやすい。
<中略>
内閣府では、潜在GDPを潜在的な資本・労働の寄与に全要素生産性を加えて計測しており、全要素生産性はHPフィルターにより平準化して求めている。また、潜在的な労働時間や就業者数についても、総実労働時間や労働力率にHPフィルターをかけたものを基に推計している。
しかし、HP フィルターは長期的に中心に回帰する傾向があるので、HP フィルターで求めた値は長期間実績値から乖離できない。このため、内閣府もGDPギャップの推計に当たっては、潜在GDPを「経済の過去のトレンドからみて平均的な水準で生産要素を投入した時に実現可能なGDP」と定義しており、GDPギャップの大きさについては、前提となるデータや推計方法によって結果が大きく異なるため、相当の幅をもってみる必要があるとしている。
HPフィルターについてCharGPTに質問してみました。
HPフィルターは、経済のデータから長期的な傾向(トレンド)と短期的な変動(サイクル)を分けるためのツールです。これは、経済が長期的に成長していく中で、その成長に影響を与える短期的な変動を見つけるのに使われます。
例えば、GDPのデータを考えてみましょう。これは経済全体の生産量を示しています。HPフィルターを使うと、そのデータから「経済が長期的にどれくらい成長しているか」(トレンド)と「短期的にどれくらい変動しているか」(サイクル)を分けることができます。
なぜこれが重要かと言うと、需要と供給が経済の変動を引き起こす要因であり、それを理解することが経済政策の立案に役立つからです。HPフィルターを用いて計算された結果を使って、経済が長期的には成長しているか、それとも需要と供給のバランスが崩れているかを把握し、必要な政策の方針を見つける手助けとなります。
簡単に言えば、HPフィルターは経済の長期的な成長と短期的な変動を見分けるツールであり、それによって需給ギャップの推定や経済の状態を理解する手助けとなります。
内閣府の潜在供給能力の計算では、HPフィルターを用いた計算により「平準化」してしまうため、どうしても潜在供給能力が過去の「低い供給能力」に引きずられて、小さい値になりがちだと言うことです。
内閣府の需給ギャップは「需要-潜在供給能力」で算出していますから、今後設備投資などにより供給能力が伸びてくると、再びマイナスになる可能性もあります。
これはマイナス成長しているわけではなく、需要の伸びを一時的に供給能力が上回ってしまうことで起きます。
また、永濱 利廣さんが指摘していますが、現在の潜在供給能力がHPフィルター平準化による過小推計であるならば、需給ギャップを適正水準にするために必要な「総需要」は、もっと大きな量である必要があります。
永濱 利廣さんは同記事で、「インフレ目標達成に必要なGDPギャップは+4%」と指摘しています。
需給ギャップから見た現状
以上の二つの理由により、現在の日本の潜在供給能力にはまだまだ余剰があり、経済対策などを実施したあと、潜在供給能力が伸びる可能性が高い事が予想できます。
必要な需給ギャップが+4%ならば、そこにたどり着くには、相当な需要拡大が必要になることになります。
名目GDPの4%なら23.6兆円に相当します。
インフレ目標達成までに、23.6兆円需要拡大しなければならないことなります。
ここまで大きな値になるのは、需要の拡大に伴い潜在供給能力も拡大するからではないかと思います。
この全てを政府支出で埋めるべきとは、思いませんが、インフレ目標の達成は思ったより、遠い道のりのようです。
なお、必要な需給ギャップの値は、経済学者やエコノミストの方々により、微妙に違う値を示しています。
永濱 利廣さんは、+4%必要と説明していますが、
高橋洋一先生は、+3%必要と、
飯田泰之先生は、+2%必要と説明しています。
このあたりが、妥当な需給ギャップの水準なのでしょう。
何れにせよ、デフレ脱却のときは近づいているので、需給ギャップを上昇させる政府支出は、大きすぎても小さすぎてもいけない「適正な財政出動」が必要な局面を迎えているのは確かです。
需給ギャップは、その適正な財政出動の規模を推定するのに必要な指標なので、よく注意して見る必要があるようです。
それにしても、経済指標を読むのは、難しいですね。頭が痛くなります。