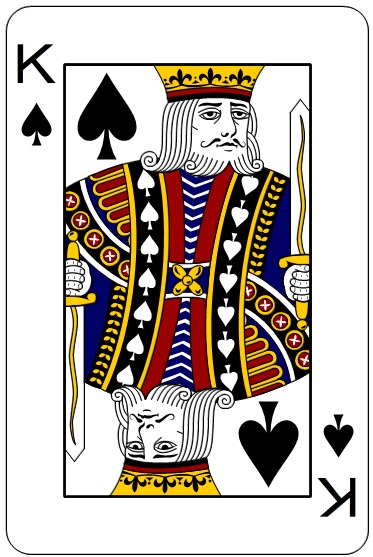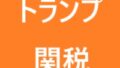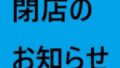米国の相互関税の導入
トランプ大統領が相互関税政策を発表しました。
日本に対しては輸入品に対して一律24%の関税をかけるそうです。
韓国は25%、台湾は32%、中国は34%、EUは20%、英国は10%だそうで、ほとんどの国が大幅な関税増税の対象となります。
トランプ大統領 相互関税日本に24% 一律10%関税【一覧表も】
この政策について、トランプ大統領は「貿易赤字の是正と国内産業の保護」「国内雇用を増やす」ことを理由として説明しているようです。
いろいろ理由を上げていますが、要するに関税増税政策です。
関税で国内産業は強くならない
これは日本の農業を見ると良く分かります。
トランプ大統領自身は「米国の製造業の復活」を喧伝しているようですが、国際競争で負けている米国製造業が関税による保護で強く成長することは通常は考えられません。
たとえば米国内ではトヨタやホンダが現地生産していますから、関税が引き上げられても現地生産の量が増えるだけで、米国内における米国資本企業の自動車のシェアはそれほど変わらないものと思われます。
関税による保護で産業が成長するなら、日本の農業は相当成長していなければおかしいわけですが、現実にはそうなっていません。
関税保護政策は、戦略物資の最低限の生産能力を維持するために行われるもので、関税により保護されている時点で、国際競争力が無い証拠であり、保護したところで強くなることはないです。
国内生産能力を強化したければ自国通貨安政策で輸出競争力を強くするか、政府からその産業に投資をして競争力を底上げする等の措置が可能です。
米国の関税強化政策で、米国製造業が強くなることはないでしょう。
これについてはトランプ大統領自身も本音では分かっているのではないかと、私は疑っています。
トランプの説明はハッタリかも知れない
トランプ大統領の関税政策についての説明は、多くのマスメディア上でエコノミスト達に否定されていて、経済学的に間違っていることは、明白になっていると思います。
関税を支払うのは輸入品を購入する消費者であり、輸出国の企業が支払うわけではありません。
関税引き上げは消費税(付加価値税)を引き上げているのとほぼ同じです。
関税引き上げは、国内輸入品物価を引き上げて、国内需要を縮小する性質があります。
日本で2014年に消費税を引き上げた翌年から消費が低迷しましたが、同じ事が起きると思います。
私は、トランプの「関税政策で貿易不均衡を是正する」「関税は外国の企業が払ってくれるので国民の負担にはならない」「アメリカは多くを外国に奪われてきた」「日本は米国からの輸入に46%の関税を掛けている」などの様々な説明は、全てハッタリだと思っています。
トランプ自身がこれらの説明を信じていないものと思っています。
おそらくトランプ大統領の関税引き上げには、裏の真意があるものと思われます。
では、それは何なのか、私なりに考えてみました。
純粋な国内経済の都合
私はトランプの関税政策を含む全ての政策は、トランプ大統領自身が言っている「アメリカファースト」に象徴される「純粋な国内の都合」を反映したものだと考えています。
表向きは関税引き上げによる貿易不均衡の是正という建前を取っていますが、実際は「国内の都合で関税を引き上げている」のではないかと思います。
米国国内の経済状況を見ると、現在の米国はパンデミック以降はインフレ率の高騰に苦しんでおり、FRBの利上げで強い「ドル高」為替になっています。
米国は財政状況が非常に悪化しており、国債発行額も多くなっている上に、米国国債は日本と違い外国に購入されている物が多く、FRBインフレ対策による利上げで国債金利の支払額も高止まりしています。
ウクライナ戦争の停戦交渉も政府支出削減を目的としたものではないかと思われます。
つまり、現在の米国は、財政再建とインフレ抑制が必要な状況にあります。
トランプ大統領の関税の増税政策は、
「貿易不均衡の是正」が目的ではなく、
「(関税)増税による財政再建」が第1の目的だったのではないでしょうか。
「貿易不均衡の是正」は「増税による財政再建」の次いでにやっているだけではないでしょうか。
本来の目的は「増税」だと思います。
実際、トランプ政権はイーロンマスク率いる「政府効率化省」による政府支出の削減政策を実施しています。これも財政再建政策です。
同盟国に対する防衛費負担の増額要求も、米国の国防費負担を削減する財政再建が目的と考えると整合性がとれます。
ウクライナ支援の削減も同様です。
本当は増税がしたいのだが、法人税・所得税・消費税(付加価値税)を増税すると選挙民の反発を買いますから、増税を直接訴えることは政治的に難しい。
そこで、大衆の経済理解が薄い事を利用して、関税の増税を行ったのではないかと思います。
今でも日米共に「関税は輸出先の企業が負担する」という説明を信じている人々は少なくないです。
関税を負担するのは輸入品を購入する消費者ですが、これが意外に理解されていません。
インフレ目標政策
日本ではデフレ脱却の為に、アベノミクスと呼ばれるインフレ目標政策を10年以上実施しています。
インフレ目標政策は、年率 2.0% 強のインフレ率を適正インフレ率とし、金融政策と財政政策を実施してインフレ率と需給ギャップを調整するマクロ経済政策です。
年率 2.0% 強のインフレ率になると、雇用が完全雇用状態の好景気になり、賃金上昇率が物価上昇率を超え人々が年々豊かになる経済状態になります。
日本のようにインフレ率が適正インフレ率より低ければ、金融緩和(利下げ)と財政支出拡大でインフレ率を引き上げる政策を実施します。
逆に、インフレ率が高すぎる場合は、金融引き締め(利上げ)と財政支出削減でインフレ率を引き下げる政策を実施する必要があります。
インフレ率が高すぎると、物価上昇率が賃金上昇率を超え人々が実質的に貧しくなってしまうからです。
米国は、高インフレで困っているわけですから、金融引き締め(利上げ)と財政支出削減でインフレ率を引き下げる必要があります。
FRBはバイデン政権のときから利上げしてインフレ抑制を実施しています。
バイデン政権のときは、FRBが金融引き締めをしているのに、政府が事実上の積極財政をしている状況で、金融政策でブレーキを、財政政策でアクセルを踏むような、矛盾した経済政策を取っていたと言えます。
ウクライナ戦争など財政支出が必要な局面だったので、これを間違っているとは言いませんが、矛盾した経済政策です。
トランプ政権の実施している政策は、政府効率化省による政府支出の削減、関税引き上げによる増税、国防負担の軽減、と何れも一貫して「財政引き締め(政府の支出削減や増税のこと)」「インフレ抑制(供給を増やすか需要を減らすこと)」に適う政策を実施しています。
FRBが金融引き締めを実施し、政府が緊縮財政を実施していますから、金融政策と財政政策の両方がインフレのブレーキになっています。
トランプ政権の緊縮財政政策は、少なくともインフレ抑制政策としては正しいことになります。
関税引き上げの影響
インフレ目標政策においては、金融政策と財政政策により、潜在供給能力と有効需要のバランスが適正になるように、調整します。
潜在供給能力の方が大きすぎるとデフレ経済になり、有効需要の方が大きすぎると高インフレになります。
潜在供給能力と有効需要はほぼ均衡している方が良いのです。やや有効需要が大きいぐらいが適正な2.0%のインフレになるようです。
だから、インフレ目標政策では2.0%強のインフレ率を目指します。
通常、高すぎるインフレでは有効需要の方が大きすぎるので、潜在供給能力の方を拡大する政策を取ります。
その方法としては生産設備投資の拡大、規制緩和による競争激化と生産性拡大、自由貿易の促進、外国人労働者の積極的受け入れ、がよく使われる方法です。
需要側を下げる政策を取ることもあります。
需要側を下げる政策として増税が有効です。国内で増税することで、消費や民間投資が減少してインフレ率が下がります。
繰り返しになりますが、日本で2014年の消費税増税では消費が低迷しました。
これは増税が有効需要を縮小することを証明しています。
トランプ政権の関税引き上げは、自由貿易の抑制なので、供給側のインフレ抑制政策とは逆の政策を実施しています。
しかし、関税引き上げは増税政策なので、需要側のインフレ抑制政策としては正しいです。
財政支出削減も需要側のインフレ抑制政策として正しいです。
もう一つ、移民の受け入れ規制を強化しているので、これもインフレ抑制政策とは逆の政策です。
これら政策に相応しいのは、デフレ脱却を目指す日本経済でしょう。
だからといって、これだけで「間違っている」とは、断定できません。
需要縮減
関税を増税すると国内で輸入品の価格が上がります。
この物価上昇はスタグフレーションでお馴染みのコストプッシュインフレなので、物価が上がっても国民の所得は増えません。
賃金が上がらない状態のまま、輸入品物価だけが上がるので、国内消費が減少します。日本の消費税増税と同じです。
消費は、有効需要の一部なので、消費が減ると有効需要が減ります。
米国へ輸出している企業は、関税引き上げ前の売上を維持するために、値下げをするか、米国内に工場を移転して現地生産に切り替えることになります。
米国は充分に需要があるので輸出していた企業は、資本力のあるところは、現地生産に切り替えてでも生産と供給を維持するでしょう。
一部の輸出企業は、輸出を諦めてしまうかも知れません。
でも、その場合は米国国内の企業がその需要に対して生産供給すると思います。
すると、潜在供給能力は維持して、価格高騰で有効需要は減ることになります。
米国は、潜在供給能力に対して有効需要が大きすぎて高インフレになっているので、有効需要が少し下がるのは、適切な政策と解釈できます。
関税増税による現地生産拡大
関税増税により、輸出企業の現地生産が増加します。
米国国内で工場を新設して、米国で製品を製造して、米国内で販売する外資系企業が増加します。
現地生産が増えると米国内の雇用が増えます。
これは、米国内の人手不足を招き、賃金上昇圧力を生じます。
これは所得を拡大しますから、有効需要が増えます。インフレ率を上げる政策です。
インフレ抑制が必要な今の米国には不適切な政策と言えます。
移民入国規制
トランプ政権は、不法移民の強制送還、不法移民入国規制強化、新規移民入国制限など「移民を減らす政策」を実施しています。
これは実質的には米国国内の労働者を減らす政策なので、国内で労働者不足を招きます。
労働者が不足すると賃金上昇圧力が高まります。
賃金が上がると国民の所得が上がるので、有効需要が増えます。
つまり、「移民を減らす政策」はインフレ率を上げる政策です。
インフレ抑制が必要な今の米国には不適切な政策と言えます。
総合的に考えると
トランプ政権の経済政策をまとめると、以下のようになります。
- 財政支出の大幅削減
- 関税増税による消費(需要)の縮減
- 関税増税による輸出企業の現地生産拡大と雇用の拡大
- 「移民を減らす政策」による賃金の引き上げ
民間投資に関しては、消費の縮減により投資が縮小する効果と、現地生産拡大により投資が拡大する効果が、両方あるので無視します。
財政支出削減(A)と消費縮減(B)は需要を減らす方向へ働きます、現地生産拡大(C)と移民減少(D)は賃上げによる所得拡大をもたらします。
増えた所得は一部が貯蓄や投資に回って、残りが消費(需要)を拡大します。
つまり、(A)(B)はインフレを抑制する効果があり、(C)(D)はインフレを加速する効果があります。
一見、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようにも見えますが、時間差を考えるとそうでもないです。
(A)(B)は直ぐにインフレ抑制効果を現わすでしょう。
しかし、(C)(D)は所得が増えてから消費に反映するまで、半年から一年ぐらいの時間がかかると思います。
また、最初は所得が増えても債務返済や貯蓄に回る率が多くなるので、すぐには消費に反映しないと思います。
つまり、高インフレに苦しむ米国では、(A)(B)の作用により、すぐにインフレ抑制効果が期待できます。
そしてしばらく遅れて、(C)(D)の効果で消費が増えてインフレ率を引き上げる効果を示す可能性が高いと思います。
関税政策を長期継続すると、後から(C)(D)の効果で高インフレに苦しむことになりますが、短期間で上げた関税をまた下げれば、適正インフレ率を達成した状態で健全な経済成長を継続出来ることになると思います。
民間投資についても、短期的には消費縮減で投資も減ると思いますが、しばらくすると現地生産の投資が始まり、投資がまた増える可能性があります。
トランプ政権の意図を推測すると
政府支出削減と、関税引き上げによる短期的コストプッシュインフレで、消費を減らして、高インフレを財政主導で抑制する。
そして、インフレ目標2.0%強付近を達成したら、関税をまた下げるか政府支出をまた増やすかして、インフレ率を安定化する政策に切り替える。
それがトランプ氏の計画ではないかと、私は推測しています。
外資系企業の現地生産拡大と、移民制限による、雇用拡大と賃上げ政策は、米国の中間層の拡大と安定に必要なので解除することはないと考えられます。
だから、関税を下げても完全に解除することは無いのではないかと思われます。
つまり、トランプ政権の意図は、財政再建と、短期的な高インフレの抑制と、中間層の所得拡大にあるのではないかと思われます。
財政政策と関税政策主導でインフレを抑制できるようになると、FRBによる金融引締めに、これまでほど依存しなくて済むことになり、短期的には利上げになっても、長期的には利下げすることになるのではないかと思われます。
所詮は素人考えです
ここに記載した推測は、完全に素人考えなので、話半分の半分ぐらいで聞いてくれれば良いと思います。
財務省の件のように、この主張を世間に広めたいとは思いません。
「言いたいことを書きたかっただけ」とお考えください。
いつも言っているように「ただの自己満足」です。
では、また。